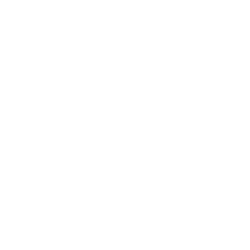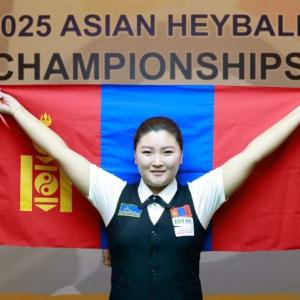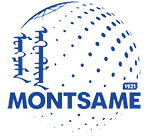井川原賢大使:日本の天皇皇后両陛下のご訪問は両国関係に新たな一章を開く
政治
(ウランバートル市、2025年7月4日、国営モンツァメ通信社)井川原賢在モンゴル日本国特命全権大使にモンゴルと日本の協力関係について話を伺った。
ーーモンゴル人はかねてより日本に興味を持っていました。大使は両国関係がいつから始まったとお考えですか。両国関係の発展の歴史の中で、どの時期が特にターニングポイントだったと思いますか。
モンゴルの方々が日本に興味を持ち、親近感をいだいてくださっていることを嬉しく思います。私たち日本人もモンゴルに対し、同じように親近感をいだいています。さて、日本とモンゴルの関係の歴史は、研究者によると遙か悠久の昔からあったそうですが、その関係を大きく変えたのは、間違いなく1990年、モンゴル民主化の年だったと言えます。今年はモンゴルが民主主義体制に移行して35周年ですが、言い換えれば、日本とモンゴルが民主主義、人権、法の支配といった共通の価値観の下で、35年間共に歩んできたことを意味します。
ーー日本政府の開発援助(ODA)により、JICA等がモンゴルのインフラ、医療、教育などの分野でさまざまなプロジェクトを実施しました。これらの中で最も具体的な成果を上げたものはどれだと考えますか。
日本政府によるモンゴルに対するODAは1977年に締結された経済協力協定に基づき実施された無償資金協力「ゴビ・カシミヤ工場建設」に始まりますが、1989年度までは研修員の受入、専門家派遣、機材供与を中心とした技術協力および文化無償資金協力といった限られた分野に留まっていました。モンゴルが社会主義体制から市場経済体制に移行した1990年以降、一般無償資金協力による積極的支援が始まるとともに、円借款が初めて供与され、日本の対モンゴルODAはさまざまな分野で本格化します。モンゴルの民主化への移行期という最も苦しい時期に日本の支援は極めて大きな役割を果たすとともに、現在に至るまで一貫してモンゴルの国造りを担う人材育成を行ってきており、2024年度までの累計支援総額は3,700億円(25.6億米ドル相当)に達しています。
どの支援も時宜にかなったものであり、高い成果を上げていますが、特に私が取り上げて申し上げたいのは、円借款の下で建設されたチンギスハーン国際空港です。
2008年E/N署名、2013年着工、2020年完工、2021年開港と、長い年月をかけて実現した656.57億円の大型プロジェクトでした。モンゴルの国際旅客数は1999年の約14万人から2024年には約175万人に増加していますが、チンギスハーン国際空港の完成により、空港の信頼性、安全性が向上し、「GO MONGOLIA」キャンペーンの推進による観光開発が進みました。

チンギスハーン新国際空港の初便記念式典
また航空貨物輸送量が増え、空港周辺開発も含めた経済効果も高く、モンゴルの国際化を新たな段階に引き上げることができました。さらに、今年1月、日本政府は、2017年にモンゴルのIMF拡大信用供与措置(EFF)の導入以降、例外を除き新規供与が停止されてきた対モンゴル円借款の手続きを再開する決定を発表しました。
これにより今後の需要拡大に応じるチンギスハーン国際空港の拡張をはじめとしたモンゴルの発展に重要なインフラ開発にさらに寄与することができると考えています。
ーー大使にとって、モンゴル社会に忘れがたい影響を与えた「草の根」プロジェクトの最も特別な例を共有していただけますか。
実は、モンゴルに対する「草の根・人間の安全保障無償資金協力」も1990年から開始されており、今年で35周年になります。これまで35年間で613案件(2024年度末時点)、供与総額は約4,800万米ドル(2024年度末時点)になります。草の根案件のひとつひとつは比較的小規模で、社会的に大きなインパクトはないかもしれませんが、地域住民に直接裨益する点でその地域の方たちにとっては大きな影響力があります。不衛生なトイレや寒い教室を草の根によって改修し、安心して教育や医療を受けられる環境を整備することは、日本政府が掲げる対モンゴルの国別開発協力方針の「包摂的な社会の実現」に合致しており、改修後に訪れた幼稚園や学校、病院で、先生や子どもたち、患者の方たちの笑顔を見られることは何よりも嬉しいことです。
ーーモンゴルと日本の間で締結された経済連携協定(EPA)の恩恵を両国はどのように活用していますか?対モンゴル日本投資の拡大のための新たな可能性は、どの分野にあると考えますか?
EPAは両国の経済互恵関係強化のための重要な枠組みであると考えています。日本モンゴルEPAを締結したにもかかわらず、貿易インバランスが縮小していないといった声を、時折聞きます。EPAは貿易や関税を自由化することで、直ちに貿易インバランスを解消させることを目的とするものではなく、投資や知的財産権保護、電子商取引、また、投資環境といった、通商分野の幅広い協力関係を促進することも含まれています。
EPAの枠組みを通じて、貿易のみならず、このような分野も含めた、経済関係を拡大させることを議論し、互恵関係を促進していくことが両国にとって重要と考えます。
昨年11月には、ウランバートルにおいて、日本とモンゴルの貿易・投資の拡大や協力関係の強化等について協議する「日本・モンゴル官民合同協議会」が開催されました。両国の経済協力を協議するセッションでは、デジタル、ヘルスケア、スタートアップ、ビジネス環境整備、日モンゴルEPAの利活用推進など、今後の協力の可能性について、日本モンゴル双方から事例も交えて議論が交わされ、これらの分野での今後の協力強化を目指しています。 加えて、現在、経済・開発省やモンゴル商工会議所との間で、日本の地方の経済団体とモンゴルの経済団体の交流を強化していくことについても、意見交換を行っています。また、今年は4月から10月までの間、「大阪・関西万博」が開催されています。万博を通じて、多くの日本人にモンゴルのことを、もっと知ってもらい、親しみを持ってもらうことを通じて、経済交流がより、拡大し深まることを願っています。
ーー両国の関係には一般市民の相互理解が非常に重要です。これは両国の関係をより明示的かつ明るく豊かなものにします。大使個人として感謝している、思い出深い日本人とモンゴル人との関係の例をお話しいただけますか。
日本人とモンゴル人の感動的な「人」対「人」の交流の話をよく聞きます。ご存じの方も多いと思いますが、日本の有名な作家、故司馬遼太郎さんとウランバートルホテルで働いていた通訳者の故ツェベグマーさんとの交流は多くの日本人を感動させました。1973年に紀行文執筆のためにモンゴルを訪れた司馬さんは、日本語通訳者のツェベグマーさんと出会いますが、そのときは両国の体制の違いから彼女の人生について詳しい話を聞くことはできませんでした。1990年に再度モンゴルを訪れた司馬さんはツェベグマーさんを取材し、「草原の記」を執筆します。彼女の人生には多くの苦しみがありましたが、しなやかに強く生きたモンゴル人女性の生き様に私たちは深い感銘を受けました。現在も、ひとり娘のイミナさんとバータルツォグトさんご夫妻は私たち家族のよき友人であり、ツェベグマーさんの遺志を継ぎ、日本とモンゴルの交流のために尽力してくださっていることに感謝が尽きません。

またチンゲルテイ区のノゴーンノール公園ではウルジートグトフさんという一般市民の方が、ご自身が利用許可を得た土地が、日本人抑留者がウランバートルの都市建設のために石を切り出した場所であることを知り、その歴史を語り継ぐ資料館を開設しています。もともと日本と何の関係もなく、歴史の専門家でもない一般のモンゴルの方が、両国関係の知られざる歴史を調べ、多くの方に伝えていこうという熱意に頭が下がる思いです。この公園は今、夏はボート、冬はスケートを地元の方々が楽しむ以外に、外国からの旅行者が訪れ、日本人抑留者とウランバートル市の歴史を知ることができる場ともなっています。 このような一般市民の交流が日本とモンゴルの関係をこれまでも、今も、これからも固くつないでいくことは確実です。
ーー日本で教育を受けたモンゴルの若者たちは、両国の架け橋としてどのように活躍していると評価しますか。
1976年に初めてモンゴルからの国費留学生が日本に留学してからまもなく50年になります。その間、日本の政府奨学金でモンゴルから約2,000 人が留学していますし、さらに私費留学も合わせると日本留学経験のある方は増えています。日本留学を終えてモンゴルに帰国した留学生の会(JUGAMO)の会員だけでも2,000人を超えています。
国費留学生や私費留学生はその後も連綿と続いてきており、その一人一人の貢献がモンゴル社会に根ざし、両国関係の促進に多大な影響を及ぼしてきています。その流れは継承されながらも、新たにモンゴルの人材育成の観点から日本政府として二つのプログラムを実施していることを紹介したいと思います。
ひとつはM-JEED(工学系高等教育人材育成支援)です。
モンゴルでは「1,000人の技術者」プロジェクトとして知られている2014年に開始した円借款事業です。この事業に基づきこれまで約1,098 人が日本に赴き、1,058 人がすでに学業、研究を終えて帰国しています。これは「点」ではなく、モンゴル経済全体の牽引ひいては産業多角化の実現という広域な「面」を対象とする人材育成を念頭においたもので、現在、今後の協力のあり方に関し議論を重ねているところです。もう一つは、2001年に始まったJDSという若手行政官育成プログラムです。これはモンゴルの行政能力を向上させるために、学生ではなく、モンゴルの中央や地方の行政組織に携わっている人たちに留学機会を与えるものであり、若手行政官としての知見に基づき日本の諸分野での成功例や失敗例を見ながら、大学で学ぶものです。モンゴルからはこれまで約430 人が参加し、すでに384人が帰国されそれぞれの行政機関や中央銀行等で活躍しております。このように拡充した制度を確実に継続しながら、流れの幅を広げていくことで、多くのモンゴルの人材が世界を舞台にモンゴルの発展のために活躍できるようになることを願っています。

ーー大使はモンゴルに初めて来てから27年過ぎました。また1991年に日本総理大臣の初のモンゴル訪問の準備に関わっていたと聞いています。それ以降、モンゴルで起こったどのような変化が興味深いと感じられますか。
モンゴルは豊かな伝統文化を継承しながらも、国際的にダイナミックに発展している点が大変興味深いと感じています。外国で学ぶことや働くことに躊躇せず飛び込む行動力があり、複数の外国語を操り、持ち前の明るさと力強さで世界のどこででも活躍されています。しかし常に母国のことを忘れず、何年か後に外国で得た知識や経験を持ち帰り、母国の発展のために役立てる方が多いと思います。今、日本で学んだり働いたりした人たちが、モンゴルの発展に寄与している姿はとてもまぶしく、希望を感じさせます。
私が1991年に西側諸国首脳の初めてのモンゴル訪問となった海部総理の訪問準備に関わった際には、新しい両国関係の創出を模索していました。
モンゴルは民主化直後のさまざまな問題に直面していましたが、私たちは常にモンゴルに対する敬意を持ち、日本としてどうやって貢献できるのか一生懸命考えていたことを覚えています。今はそのときに比べると、積み重ねてきた信頼関係が確固たるものとなっており、あらゆる分野で日本とモンゴルが手を携えてきたこと、パートナーとして歩んできた歴史が底流にあることに安心感を覚えています。
ーー日本の天皇皇后両陛下が麗しい夏の季節に美しいモンゴルを訪問する予定です。これは両国関係をどのような新たなレベルに至らしめるとお考えですか。
天皇皇后両陛下の御訪問は、日本とモンゴルの二国間関係を記す歴史書に、金の文字で記されるべき意義深い出来事です。まず、ナーダムも開催される7月のすばらしい時期に御訪問いただけるということは、モンゴルの方たちにとって大変誇らしいことだと思います。モンゴルの方たちが最高のモンゴルを天皇皇后両陛下に見ていただきたいと敬愛を持って歓迎していただけることが、私にとっても大変嬉しいことです。
次に、天皇皇后両陛下がモンゴルの方々の熱意に応えてくださったということは、両陛下がモンゴルをいかに大切に思ってくださっているかの現れではないかと考えています。
実は両陛下は即位されて7年になりますが、国際親善のための外国御訪問されたのは2023年のインドネシア、2024年の英国に続き、モンゴルは3か国目の栄誉となります。今回の御訪問は、これまでさまざまな交流により培われてきた日本とモンゴル両国の関係の新しいページが開かれるきっかけになります。両陛下の御訪問を前に、私たちの世代が先達たちから受け継いだ日本とモンゴルの信頼関係に基づいた恩恵をそれ以上の深さ、広さにして次の若い世代に引き継いでいきたいという決意を新たにしています。
ーー両国関係の未来をどのように想像し、期待していますか。
日本とモンゴルは、平和と繁栄のための特別な戦略的パートナーです。両国が、アジアにとって、さらには世界の中で、最も平和的で、最も民主主義的で、最も豊かな文化的なものを発信できるパートナーとして共に存在し、その魅力を輝かせていく未来が私の願いです。
モンゴルは多くの国々と広く交流ができる利点があります。日本は私が思うに最も平和志向で独自の文化を持ちながら人類の平和のために貢献していこうという気持ちが強い国です。
そういった両国が今、良好な信頼関係を構築していますが、これを我々が次世代も、次々世代も、50年後も、100年後も更に充実した方向へと発展せしめて、モンゴルと日本それぞれがアジア地域で、また国際社会の中で、最も魅力的なものを発信し、国民もそれを享受している国として、またパートナーとして存在し続けていくこと、そして世界中がそれを認知して、日本とモンゴルの関係を賞賛する時がくることが私の夢です。
 Ulaanbaatar
Ulaanbaatar